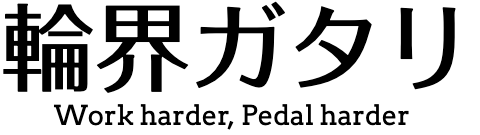自転車を構成するフレーム、ハンドルやホイールといったパーツは、長らく欧米のブランドが台頭する時代が続いてきた。しかし、2000年代以降、欧米ブランドがアジア圏の工場へOEM製造(=Original Equipment Manufacturer:相手先ブランド製造)を委託することが増えたことを背景に、中国や台湾の新興メーカーは欧米ブランドのノウハウや技術力を吸収して成長し、近年ではオリジナル製品をグランツールに供給するメーカーも現れたほどである。
中国や台湾の新興メーカーは、人件費や製造コストの低さを生かして、価格が低く性能が高い製品を製造できることから、しばしば市場を賑わせてきた。しかしながら、販売経路が海外からの直販に限られているために、輸入代理店で販売されている製品と比較して入手のハードルが高いことが一般的であった。これは、流通コストをカットすることで販売価格を下げるためのメーカーの意向であることが多い。しかしながら、こうした新興メーカーをあえて取り扱い、国内のユーザーに向けて販売する輸入代理店も登場してきている。
本記事で取り上げるBOOTLIGHT BICYCLES(以下、ブートライトバイシクルズ)は、中国の新興メーカーを専門に取り扱う輸入代理店である。今回は、ブートライトバイシクルズの代表を務める奥田直継氏に、立ち上げるに至った経緯と、あえて新興メーカーの輸入代理店をビジネスとする意義、そして自転車産業における新興メーカーの現在の立ち位置と今後の展望などについて、話を聞いた。

いちユーザー視点から、輸入代理店ビジネスの創業へ
——まずは、奥田さんの自転車との関わりを教えてください。
奥田 自転車は大学から競技として始めました。大学生時代は自転車部に所属し、学連(=日本学生自転車競技連盟)に登録してレースにも参加していました。
——大学卒業後には、レーサーとしてのキャリアを進まれたのでしょうか。
奥田 いえ、新卒では自動車の部品メーカーに就職し、エンジニアとして働いていました。
クラブチームに所属してプロレーサーとして活動するようなキャリアも検討しましたが、レースへの参加を通してクラブチームの選手の生活の実情を目の当たりにする中で、欧米などの海外と比較して自転車ロードレースの盛り上がりに欠ける国内では難しいと思うようになりました。そこで、高校時代から工業系エンジニアに憧れを持っていたこともあり、一般企業に就職してエンジニアとしてのキャリアを進むことを選びました。
——自分でビジネスを興そうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。
奥田 サラリーマン生活の中で、自分のスキルに応じた評価が得られないことに対する不満感や不公平さを覚える場面が増え、自分でビジネスを作り上げ、自分で管理していきたいと思うようになったことがきっかけです。もともと学生時代から起業したいと考えていたこともあり、これを機に輸入代理店のビジネスをやってみようと一念発起して2023年8月に独立しました。

——ブートライトバイシクルズの創業はお一人でされたのでしょうか。
奥田 いえ、大学時代にレース活動を通して知り合った友人の中西優人さんと一緒に始めました。ちょうど彼も独立して自分のビジネスをやりたいと言っていたタイミングであり、彼とは学生時代から考え方や価値観に共通点が多かったこともあったので、一緒にビジネスをするパートナーとして最適だと思い、一緒にやろうと声をかけました。現在は、中西さんがテクニカルな面を担当し、私が商材探しやオンラインショップの管理、およびビジネス全体のマネジメントを行っています。
——なぜ中国の新興メーカーに絞って取り扱うことにしたのでしょうか。
奥田 安価で品質の良い中国ブランドの部品を、直感的に探すことに長けていると自負していたためです。お金の無かった学生時代に、安価な自転車部品をAliExpress(=アリエクスプレス:主に中国のメーカーや販売業者の製品を取り扱う通販サイト)で探して購入することが多かったので、玉石混交な製品の中から信頼できるメーカーの特徴を探し出すノウハウを身につけられました。また、国内には中国ブランドの製品に対して不信感を持っているユーザーも多かったため、安くて良い製品が存在するということを世間にもっと広めたいと思ったことも理由の一つです。
——ブートライトバイシクルズで商材を探す際の決め手について教えてください。
奥田 誰も手をつけていないメーカーであることが重要です。たとえばELILEE(エライリー)社の製品は、我々が代理店契約を最初に始め、現在ではメインの商材の一つになっています。他にも、可能であれば独占的に契約が可能であることも重視しますが、現在のブートライトバイシクルズのビジネスの規模では、フレームなどのSKU(=Stock Keeping Unit:サイズ・色などの種類の多さを表す単位)が大きい製品をラインナップしているメーカーとは独占契約が難しいことから、メーカーの規模感を考慮して探しています。

ブートライトバイシクルズの存在意義とは
——国内の輸入代理店を通して購入することは、直販での購入と比較して、ユーザーにとってどのようなベネフィットがあると考えていらっしゃいますか。
奥田 まずは、国内にまとまった量の在庫が確保されているために納期が明確であるという点がベネフィットです。特にメーカー直販では納期が製造のタイミングに左右されることがあり、購入手続き後にいつまでも到着しない事例も聞かれましたが、国内購入であればそういった不安を感じずに購入が可能です。
また、製品のサポート体制においては、メーカーサイトや通販サイトなどでは不足している製品の規格や互換性などに関する補足情報の説明、製品の問い合わせ対応、さらに製品保証の提供も行っています。
——価格面ではユーザーにとって不利な面もあるのでしょうか。
奥田 価格については、通販サイトと価格を合わせるようにしています。一般的には、輸入代理店を経由すると直販や通販よりも価格が上がることが多いですが、ブートライトバイシクルズではユーザーにとってコスト増にならないことを意識しています。
——メーカー側にはどのようなベネフィットがあるのでしょうか。
奥田 日本のユーザーからの問い合わせの窓口としてブートライトバイシクルズが機能することで、メーカーにとっては直接カスタマーサポートをしなくてよくなる点がベネフィットになります。メーカーに代わって手厚く説明をすることで、ユーザーにとってもより分かりやすくなり、メーカーともユーザーともWin-Winの関係を構築しています。

中国ブランドは欧米ブランドを超えられるのか?
——日本の自転車業界における中国ブランドの現在の立ち位置について教えてください。
奥田 近年の品質向上に伴って、中国ブランドの製品は国内市場における地位を確立してきていると思います。中国ブランド製の低価格帯の製品群が市場に多く出回るようになったことで、名門欧米ブランドがそのポジションを揺るがされる事態になっているほどです。さらに、これまで低価格帯がウリであったメーカーが機能向上に伴って高価格帯にシフトする流れもあります。しかしながら、中国ブランドの製品がハイエンドな欧米ブランドを超える地位をすぐに確立することはないのではと考えています。
——そう考えられる理由はなんでしょうか。
奥田 ハイエンドな欧米ブランドと、新興の中国ブランドでは研究開発の規模感が大きく異なっているためです。先進的な研究開発の環境が整っている欧米のブランドは最先端技術を確立し、技術のトレンドを生み出すことができます。一方で、研究開発の規模が小さい中国ブランドは技術の後追いになり、エビデンスのない新たな技術を作り出すことは現時点ではできないためです。現在の中国ブランドの躍進は、製品の目新しさによって注目されている面もあり、技術を含めた製品の良さとして欧米のハイエンドブランドと比較されるまでには、今後10年程度かかるのではと考えています。

——今後の中国ブランドの展望を教えてください。
奥田 自社ブランドとして現在流通しているメーカーよりも安価に製造できる、まだブランドとして確立されていない新興メーカーが多く存在しています。最近では、日本人がこういったメーカーにOEM製造を委託し、新たなブランドを立ち上げるケースも増えています。今後は、まだ日の目を見ていないメーカーの取り合いも起こるかもしれません。
新たなメーカーがそういったOEM製造を通して成長し、将来的に自社ブランドとして確立していく、というエコシステムが回っていくのだと思います。
——今後のブートライトバイシクルのビジネスの展望について教えてください。
奥田 新興メーカーの製品は、まだまだニッチなパーツが多いことから、熟練のサイクリストへの認知度は上がっている一方で、学生や初心者にはまだまだ届いていないと考えています。今後はそういった方々にも届けるために、パーツ単体ではなく、完成した車体として提案していきたいと考えています。
——奥田さん自身の今後の目標について教えてください。
奥田 これまでのブートライトバイシクルズでの活動では、中国ブランドの中から面白い製品を探し出してお届けしてこられたと感じます。しかしながら、輸入代理店業ではメーカー側のモノづくりに介入することは難しく、ビジネスの自由度に限界も感じます。そこで、今後はブートライトバイシクルズの活動とは独立して、オリジナルのパーツブランドを立ち上げたいと考えています。まずは、これまでのノウハウを生かして選定したメーカーでのOEM製造で作っていくことを考えていますが、将来的には日本国内で研究開発および製造を行い、海外に誇れるようなブランドを作り上げていきたいです。

(了)
Interview, Text & Photo ●moving_point_P(ponkotsu)