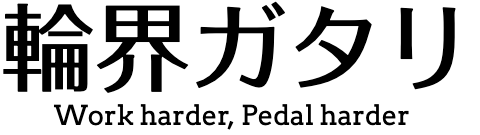株式会社イルカは、2019年に折りたたみ自転車ブランドirukaを発表すると、すぐに海外への販路を広げ、2022年には延べ出荷高(小売価格ベース)が1億円を超えた。 その創業者であり、iruka設計者でもある小林正樹氏は、イルカ創業までに輪界との関わりがほとんどなかった人物である。小林氏はどのようにして折りたたみ自転車の設計開発に携わるようになり、irukaを製品化するに至ったのか。独自の折りたたみ機構を持つ車体の開発の裏側や、実際の生産から量産に至るまでの紆余曲折について話を聞いた。

いちユーザーから開発者へ
——まず、小林さんと自転車の関わりについて教えてください。
小林 出身地の静岡市では自転車の利用率が高く、私も中学・高校は自転車で通学していました。
当時は自転車を単なる移動手段としか捉えていませんでしたが、30代の頃にDAHONの折りたたみ自転車を買って自転車通勤や輪行を始めてから、自転車そのものに対する興味や愛着が湧いてきました。
——ご自分の自転車を整備しながら、開発のための知識を身につけたのでしょうか。
小林 DAHONで輪行旅行に行くことはあったので、簡単なメンテナンスは自分でできるようになっていましたが、自分で複雑なカスタムをするような整備の経験を積むことはありませんでした。
irukaの開発は、自転車の設計や生産に関する知見がほとんどない状態から始めました。
——irukaの設計の際に困難はありませんでしたか。
小林 最初は右も左もわからない状態でしたが、自転車の設計経験が豊富なプロダクトデザイナーと協業したことが助けになりました。
工場からの部品の入手や製品の不良率に関するアドバイスを受け、それを設計にフィードバックすることで、量産に漕ぎ着けることができました。

これまでの常識では「作れない」自転車を作る
——irukaが完成するまでの過程について教えてください。
小林 当初の設計案はモールトンのようなトラス構造のもので、現在のirukaの設計とは全く異なるものでした。
その図面をもとに、有力視していた台湾のOEM(=Original Equipment Manufacturer:相手先ブランド製造)工場に打診しましたが、設計が細部まで十分に考慮されていなかったことや、先方が自社ブランド製品の開発に手一杯であったことなどから、交渉が上手くいきませんでした。
現在のirukaに近いものに設計を変更したのち、台湾の別のOEM工場に打診しましたが、ここでも交渉は上手くいきませんでした。特に海外の工場に製品を理解してもらう過程で実車の必要性を実感し、日本の工房で手作りのスケルトンモデルを製作しました。それをもとに、今度は中国の工場で試作をしたり、製造について交渉したりしていたのですが、製造工場の責任者の解雇などもあり、3社との交渉が続けて頓挫してしまいました。
その後、現在の製造元でもある台湾の工場と契約することができ、2016年ごろには基本設計を固めることができました。そこから約2年にわたってフレームの表面処理などの細かな検討を重ね、2018年に現在のフレームの製造を開始できました。量産に至るまでには最終的に8世代の試作車を作りました。

——製造工場はどのように選定し始めたのでしょうか
小林 当初は当てがなく、I社やT社など、折りたたみ自転車を製造する国産メーカーに連絡を取り、直接訪問して自転車の製造工程について伺い、自転車製造工場の選別の過程や組み立ての工程などについて教えて頂きました。
伺っているうちに、自転車製造工場がほとんど無くなってしまっていた日本国内では、自転車のフレームを作れないと判断し、中国や台湾の工場を探すようになりました。

——具体的にはどのような点が変更されていったのでしょうか。
小林 検討箇所は数多くありました。例えば、当初はフレームのメインチューブを2本のパイプを繋いでいましたが、押出成形を用いた一体型のチューブに変更しました。
また、フォークも初期は右持ちだったものを現在の左持ちに変えたことで、前輪を折りたたむ方向も右折りから左折りに変わりました。一方で、「小径車でありながら中距離の走行性能が高いバイク」という開発コンセプトは一貫していました。

——工場の選定にあたって苦労した点はありましたか。
小林 irukaは独自の折りたたみ機構をもつため、独自の部品が多く必要になりました。
こういった新しい構造の自転車は、開発期間が長くなりますし、工場側の開発時間と人的リソースも多く必要になります。工場からすれば、多大なコストがかかる上に、長期間にわたって開発費を回収できない可能性もあり、多くの工場に製造を断られました。また、工場経営者と前向きに話を進められていても、製造の担当者とやり取りをすると話が進まなくなる、というケースも大変でした。
担当者が図面を見て「作れない」という判断をしたとしても、メンツを強く気にするお国柄からか、担当者自身の口から「これは作れない」という言葉はなく、結果として放置されてしまうんです。そのような背景が理解できるまで、工場からの返答を数か月待つことがたびたびありました。
——当時を振り返って、製造に関する知識があった方がよかったと思いますか。
小林 生産に関する知識を最初から持っていれば、もっと早く完成に漕ぎ着けられていたかもしれません。一方で、知識を持っていると、「理想のもの」よりも「作れそうなもの」を優先してしまったかもしれません。知識に囚われなかったからこそ、現場に「作れない」と判断されてしまうような設計の自転車を作ることができた、という面もあると思っています。

(了)
Interview&Text●moving_point_P(ponkotsu)
Proofreading●Kohei Matsubara
Photo●KuroMino, Masaki Kobayashi